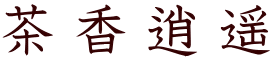兜改め
宇治・丸久小山園のお茶を飲みながら、宇治と云えば抹茶、そして世界遺産・平等院、さらには平等院境内の入口近くにある「扇芝」へと想いは連想ゲームのように繋がって行きました。(少々、強引です…)
「扇芝」は、宮中の鵺(ぬえ)を射落したという伝説が残る源頼政(みなもとのよりまさ)が自刃したといわれる扇形の場所で、石碑が置かれています。
因みに、源頼政は組香「菖蒲香」の証歌となっている「五月雨に…」の歌でも知られている文武両道の平安末期の武将です。
自刃のお話は、皇子を奉じて平氏打倒の兵をあげるも敗走を重ね、戦の末に平等院で最早これまでと扇を置いて命果てるのですが、頼政の最期は『平家物語』の「宮の御最期」に詳しく描かれています。
物語には、自刃後の頼政の首を家来の長七昌が取って、石にくくりつけ宇治川の深きところに沈めたとあり、武将の首を敵方に取られることを恥とした武士の想いが伝わってきます。
幸いにも?頼政の首は宇治川の水底に眠ることになったようですが、実際に戦となると多くの武将が討ち取られることになり、事後には武将の確認のため「兜改め」と称することが行なわれていたようです。(いつの時代から行なわれていたのか知りませんが…)
「兜改め」とは、
①兜首(かぶとくび)の兜を検査して、その主の身分などを査定すること。
②浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」の大序(だいじょ)の俗称。また歌舞伎の同場面の通称。
と広辞苑にはあります。
兜首は、兜をつけるほど身分のある武将の首ということになりそうですが、討ち取った数が多い場合には兜が誰のものか判じ難く、兜に焚きしめた香りで、その主を決めたという物語があるようです。(兜の造作でも分かりそうなものですが…)
歌舞伎の名作「仮名手本忠臣蔵」は、物語の舞台を室町時代に設定して、その大序(一段目)では高師直(こうのもろのう)が塩冶判官(えんやはんがん)の正室・顔世御前(かおよごぜん)に横恋慕して言い寄るも断られたことを根に持って、松の廊下の刃傷沙汰に及ぶことを窺わせるような設定になっています。(因みに、高師直=吉良上野介、塩冶判官=浅野内匠頭です)
大序では、新田義貞の兜改めの際に、かって仕えていた顔世御前が呼び出され、義貞は伽羅を焚きしめていたとして香りから兜を特定する場面があります。(舞台上では、兜の造作も一際立派なものでした)
「仮名手本忠臣蔵」が書かれたのは江戸時代ですから、物語の上で伽羅を焚きしめるという設定に全く無理はありません。
でも、室町時代に武士が出陣にあたって、兜に伽羅を焚きしめていたのかどうか、練香の空薫はどうであったのか等々、本当のところはよく知りません。
図書館でDVD『仮名手本忠臣蔵』を借りて観ましたが、名作と云われるだけあって、舞台演出も素晴らしい、実に荘厳な物語になっていました。
■
「兜改め」については、二年前の読売新聞に掲載された日本史家・磯田道史氏の随筆を今でも思い出します。
「古今をちこち」と題するもので、見出しは「”信繁”も加わり兜に香」。
1615年の大坂夏の陣で豊臣方の武将・木村重成が兜と黒髪に空薫(そらだき)で香りを焚きしめて出陣、討ち取られた彼の首からは香薫が漂い、後世の語り草になった旨が書かれています。
実は、この随筆のメインは、木村重成の故実を受けて、実際に兜に香を焚きしめる実験を行なったところにあります。
実験には当時NHK大河ドラマ「真田丸」に出演していた”信繁”役の堺雅人も駆けつけ、兜の下で伽羅の香木を焚いて香気を移す試みがなされたそうです。
結果はというと、伽羅の香木に火をつけたため白い香煙があがり、兜には伽羅の香りは確かにあるものの「割り箸を燃やしたようなこげ臭さ」があったのだそうです。
実験結果を受けて、「伽羅などの香木でなくむしろ練り香などで時間をかけてゆっくり香気を兜にうつしていった方がよいのではないか」という結論に至ったとか…。
云われてみると、香木といっても木材ですから、火をつけたら燃えそうな感じがします。
聞香でも、火相が強いと香木から白煙があがり、確かに焦げたにおいがします…。
磯田氏の随筆の最後は、実験を終えてから聞香を行なったところ、一番になったのは堺雅人氏で「一芸の達人はすごいものだと思った」という一文で締めくくられています。
同随筆のPDFです。面白いです。 →![]() 2016.03.16yomiuri
2016.03.16yomiuri

※地植えの野萱草が咲いています。