方目とは
ネット上にある志野流香道の組香目録をみると、組香は内十組、三十組、四十組、五十組、外組、外盤物十組で構成されています。
それらの内、外盤物十組にある「鷹狩香」は鷹を携えた人形が、聞きの当りに応じて盤上を進み、鳥を捕らえるような仕立てになっているようです。
鳥は十羽で、ある古書には、鶴(靏)、雉、鷺、雁、山鳥、鴨、鴫(しぎ)、鶉、鳩、方目とあります。
方目…?
なにコレ?
『広辞苑』と『日本国語大辞典』で、読みを変えて、字体を変えて、いろいろ調べてみましたが「方目」は出てきません。
ネットで検索しても引っ掛かりません。
別の古書では、「方目」の所が「鸞(らん)」になっていたりします。
※鸞=中国の想像上の鳥。鶏に似て、羽の色は赤色に五色を交え、声は五音に合うと伝えられる。(広辞苑)
浄土真宗の開祖「親鸞」の「鸞」です。
また、徳川美術館発行の「香の文化」展覧会図録では、「方目」の所が「鶯(うぐいす)」となっています。
「方目」の読みとどういう鳥なのかが気になって、夜もおちおち眠れません。ホント? (^^)
こんな時、困った時には、諸橋轍次『大漢和辞典』が最強で最後の拠り所となっています。
図書館に出かけて、「方」の項を調べたところ、「方目(ほうもく)」は確かにあって、三番目の意味として「鳥の名。みぞこひ」とありました。
みぞこい?
何?この鳥は…?
『広辞苑』には「溝五位(みぞごい)」としてサギの一種とあり、写真も載っていました。(^^)
「方目」騒ぎは、とりあえず一件落着となりました。
さすが!諸橋轍次『大漢和辞典』様様です。
『大漢和辞典』には、「方目(ほうもく)」の項で「みぞこひ」の他の名として、偏「方」に旁「鳥」のホウ(ミゾゴイサギ)、そしてウスメ【護田鳥】(ミゾゴイ・ゴイサギの古称)もありました。
とりあえず怪傑(解決)黒頭巾です!
4月から始まった外盤物シリーズの最後は【鷹狩香】です。
外盤物十組⑩【鷹狩香】
◆香三種
春狩として 六包に認め内一包試
冬狩として 同断
鷹として 一包に認め無試
◆聞き方
試みを終え、春狩・冬狩の十包を打ち交ぜて内から一包を抜き、鷹の香を加えた十包を又打ち交ぜて炷き出します。
一炷開きです。
◆記録(当りだけを記す)
| 春冬冬春冬冬冬春鷹春
札名 春 冬春 冬冬
◆盤
盤一面、人形十(狩装束で鷹を持つ)、鳥十羽(鶴・雉・鷺・雁・山鳥・鴨・鴫・鶉・鳩・□)※□は方目、鸞、鶯?
平成8年に名古屋・徳川美術館で「香(かおり)の文化」展が開催されました。
同展図録には東京国立博物館蔵「十組盤」の写真が載っています。下は「鷹狩香」の盤一式です。
解説には、「十人の鷹匠が手に鷹を据えて駒を進め、反対側の獲物である鶴、雉、雁、鷺、山鳥、鴨、鴫、鶉、鳩、鶯をとって帰る」とあります。
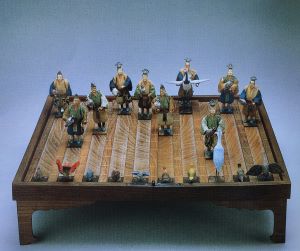
盤物は盤一式(盤・人形・立物・札)があってこそビジュアル的にも楽しめる組香かと思います。
外盤物十組の盤一式が現代にどの程度受け継がれているのか、門外漢ながら興味深いところです…。 (^^)
今日の名古屋の最高気温は31.5℃。
文句なしの?真夏日となり、エアコンの試運転と相成りました。
今夏もなんだか暑そうです!
堪忍!
暦の上では昨日が「入梅」でした。
でも、東海地方はまだ「梅雨入り」の発表がありません。
天気予報を見ると、今週末当りどうやら梅雨入りとなりそうです。 (^^)
