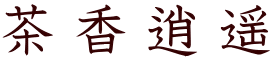香りを「聞く」-聞香-
時雨の中、山茶花の一番咲きです。

香道では香りを「嗅ぐ」とは云わず「聞く」と云っています。
志野流香道先代家元・蜂谷幽求斎宗由宗匠(1902~1988)が月刊誌に寄稿された「香道の心得」の中に、香りを「聞く」と云うようになった経緯が興味深く記されています。
香道の心得 ◆霜月◆ (4)
物の音を「聞く」といえば極く普通のことだが、さて香道でいう香りを「聞く」―聞香―となるといかにも不可解なことにおもわれてしまう。
確かに上代でも、「五月待つ花橘の香をかげば」(古今集)とか「匂いどもの勝れたらむどもをかぎ合せて」(源氏物語)といって香り、匂いはかぐであり、鎌倉時代になると「聞香」の文字が現われ「聞き」の字をあててはいるもののかぐと読んでいるようである。やはり“聞香”の語は仏典にしばしば記載されているように漢語であり、ぶんこうあるいはもんこうと音読すればよいが、和訓するなら香をかぐと読むべきだそうである。ところが“家風”(かふう)をいえのかぜと誤り読むように、きくと文字読したことから香はきくと言いならわしたといわれている。あるいは香道の立場から、殊さら香木のかおりを高邁なものにする作為からであったかもしれない。聞くと盛んに言い出したのは、浮世草子などにも見られるように江戸時代に入ってからのことらしい。
“聞”の語には物事を見極めるとの大意がある。だから“聞香”は、「香りの美の鑑賞と追求に始まり、正しく聞き判じ、少しでも香を聞く」の本質に近づかねばならないことになろう。
※“聞”の語は、中国唐代詩人・杜甫(712~770)の「大雲寺賛公房四首 其三」の一節「心清聞妙香」にも見ることができます。
意味は「心清らかにして妙香を聞く」でしょうか。
燈影照無睡,心清聞妙香。
夜深殿突兀,風動金瑯璫。
天黑閉春院,地清棲暗芳。
玉繩迥斷絕,鐵鳳森翱翔。
梵放時出寺,鐘殘仍殷床。
明朝在沃野,苦見塵沙黃。
※個人的には、「香道の心得」の文中で思わず頬が緩んでしまった一文があります。
「あるいは香道の立場から、殊さら香木のかおりを高邁なものにする作為からであったかもしれない。」
香道の奥は深そうです…。(^O^)