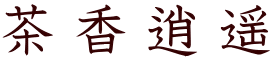法隆寺(太子)は赤栴檀?
今日から10月。
いよいよ秋!と云いたいところですが、今日の名古屋の最高気温は31℃台の真夏日となりました。
でも、陽射しは矢張り柔らかく、夏の厳しい暑さから抜け出たような感はあります。
10月の声を聞くと、今年も残すところ3ヶ月、月日の流れの速さには驚いてしまいます…。
先日のことです。
「香木の法隆寺は赤栴檀?」との声が聞こえました。
「えっ?」
思いもかけないことでした。
赤栴檀(しゃくせんだん)と云えば、香りの聞きをリセットするための隔香という認識しか持っていなかったので、即座に返答できなかったのです。
あの名香とされる「法隆寺」が赤栴檀?
改めて名香一覧を見てみました。
名香として名高い「法隆寺」(別名:太子)は、いわゆる六十一種名香一覧の筆頭に位置しています。(二番目が東大寺)
木所は佐曽羅(さそら)、味は[酸苦甘]とあります。(酸が第一です!)
香木の特徴は六国五味で分類され、六国は香木が渡来してきたとされる伽羅(きゃら)・羅国(らこく)・真南蛮(まなばん)・真那賀(まなか)・佐曽羅(さそら)・寸門多羅(すもたら)の六つの地名(木所)で、味は香木を炷いたときの香りを甘・酸・辛・苦・鹹の五つの味で表現しているようです。
「佐曽羅?」
「佐曽羅ねぇ~」と呟きながら、六十一種の香銘を眺めていて、ふと気付いたことがあります。
木所(きどころ)が佐曽羅のものは、六十一種名香の中では「法隆寺」だけなのです。
百二十種では?、二百種では?、と調べてみたのですが、佐曽羅は法隆寺だけのようです。
「どうして…?」
この香木で聖徳太子の像が作られたとも云われている「法隆寺」ですから、六十一種名香に属していても不思議ではありませんが、これまで佐曽羅であることを全く意識していなかったのです。
勿論、香木「法隆寺」の香りは聞いたことがありませんし、写真を見たことさえありません。
香木はあるところにはあるのでしょうが、「秘してこそ花」の類なのかもしれません。
辞書には、赤栴檀は「白檀の赤味がかった心材」とあり、「六国(りっこく)では佐曽羅に分類される」とあります。
更に、「名香法隆寺(太子)は赤栴檀とされる」とも記してあります。
三段論法です。
法隆寺(太子)は佐曽羅であり、佐曽羅を赤栴檀とすると、法隆寺(太子)は赤栴檀、ということになります。
分類上は、沈香ではなく、白檀の類ということになりそうです。
でも、なんとなく腑に落ちません…。(^O^)
赤栴檀に分類される香木を隔て香として、昨年の志野流香道全国大会名古屋大会で聞いたことがあります。
名香席で「紅塵」(伽羅)と「一聲」(伽羅)の隔て香として、間に赤栴檀が炷かれたのを聞いたのですが、これが素晴らしい芳香で白檀の類とは思えなかったことを覚えています。
茶の湯で使う「白檀」系の香りとは異質だったように記憶しています。
そう、印象に残るいい香りだったのです。
ところで、佐曽羅および赤栴檀は名古屋・徳川美術館に大量に所蔵されています。
平成八年に催された「香の文化」展には香木が多数出展され、同図録に掲載されています。
 ※佐曽羅/一番上の香木の重さは1519グラム。
※佐曽羅/一番上の香木の重さは1519グラム。
 ※赤栴檀/重さは1257グラム。
※赤栴檀/重さは1257グラム。
佐曽羅と赤栴檀がきちんと区別されているという事は、両者には違いがあると云うことになります。
経験と知識に富んだ宗匠方が、「これは佐曽羅、あれは赤栴檀」と分けられたということでしょうか。
佐曽羅と赤栴檀の香りがどのように異なるのか、一度、両方の聞き比べをしてみたいものだと思いました。
とは言っても、香りは一様ではないので、香りを一度聞いただけで、判じられるような代物でないことだけは容易に想像できますが…。(^O^)
六国は、深~い闇の底に沈んでいるような気が段々してきました。
どうしましょう…。
詩歌をちこち 【菖蒲香】
[証歌]
五月雨に池のまこもの水まして 何れあやめと引ぞわづらふ|『太平記』巻第二十一 「塩冶判官讒死事」に頼政の歌
五月雨(さみだれ)に澤邊(さわべ)の眞薦(まこも)水越(こえ)て何(いづれ)菖蒲(あやめ)と引(ひき)ぞ煩(わづら)ふ*出典『日本古典文学大系』(岩波書店)
※源頼政(みなもとのよりまさ)
※『国民の文学11 太平記』尾崎士郎訳(河出書房新社)には、「塩冶(えんや)判官(はんがん)讒死(ざんし)事」の件が現代語訳であります。
上記の歌が詠まれたのは、病気で出仕をやすんでいた高師直(こうのもろなお)を慰めるために催した酒宴で、二人の検校が「平家」を詠った物語の一節に出てきます。
歌が詠まれるにいたった場面、経緯は省略しますが、頼政が詠んだ歌を聞いた近衛関白が感に堪えかね、みずから席を立って菖蒲の前の袖を引き、「これが、その方の妻じゃよ」と教えて頼政に賜わり、頼政は鵺(ぬえ)を射て弓矢の名を揚げたばかりでなく、一首の歌を詠んで.御感に叶い、年ごろ心ひそかに思いをかけていた菖蒲の前を手に入れたことは、まことに名誉なことである、と訳してあります。
物語はその後、菖蒲の前が本当に美しかったのかどうかの品定めが続き、侍従の女は、もし菖蒲の前が本当に絶世の美人であれば千人万人の女が並んでいようが頼政は見分けられないはずがない、などと続いています。
実は、頼政は美女十二人の中から、菖蒲の前を見分けていたのですが、あえて上記の歌を詠んだという見方があります…。